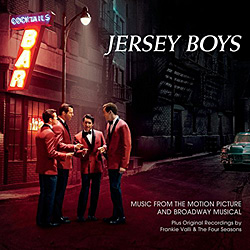小規模ウエディングにおける音楽の価値
みなさん、こんにちは!
9月になりましたがお元気でしょうか。久しぶりの更新になってしまいすみません!
緊急事態宣言の延長に伴い、9月に入っても結婚式の日延べが相次いでいる会場も多いのではないでしょうか。
首都圏を中心にアルコールの提供ができない今の披露宴の中、「披露宴=祝いの場=酒宴」という、これまで当たり前だった考え方にも変化が生じています。
ドリンクに関して言えば、例えばノンアルコールのレパートリーを豊富に揃える、各会場の特性を活かした「らしさ」のあるドリンクの開発、提供など工夫している会場が多い様です。
「これができない。。。」とネガティブに捉えるのではなく、「こんなこともできますよ」と逆に提案の幅を広げるチャンスでもあり、ウエディングに携わる人は今その資質が求められているのかもしれません。
こういった変化への対応はドリンクだけではなく、私が直接携わる披露宴の演出においても同じで、披露宴の音楽演出においてもそうだと思います。
日延べ前には、多くのゲストを招いて、余興などの演出で盛大な披露宴を開催する予定が、小規模で親族や親しい友人のみの食事会を中心としたものに変更している披露宴が多い中、会場の雰囲気を作る上で大きな要素となる音楽(BGM)はそのままで良いのか、と私は思っています。
披露宴の音楽においても、おふたりの真意をしっかりヒアリングし、提案する力が今求められていると思います。
親族のみの小規模な食事会がメインの披露宴の場合、よりアットホームな和やかな雰囲気を披露宴のイメージとして持たれているおふたりが多い様に感じます。その場合は、BGMも当然ながらそのような雰囲気に適した音楽の選曲がより適していると言えます。
例えば、この「アットホーム」という言葉一つとっても、そこに込められた想いはカップルによって異なる場合があります。だからこそ、先にも書いた通り、おふたりの真意をしっかりヒアリングし、音楽によってできる演出と効果をしっかりおふたりにお伝えすることが大切であると考えています。
各シーンに込めたおふたりの想いやストーリーを意識して選曲すると演出効果も高まり、より感動が生まれるものです。音楽にはそんな不思議な力がある、私はそのように信じています。
![]()
◆3-yui(みゆい)
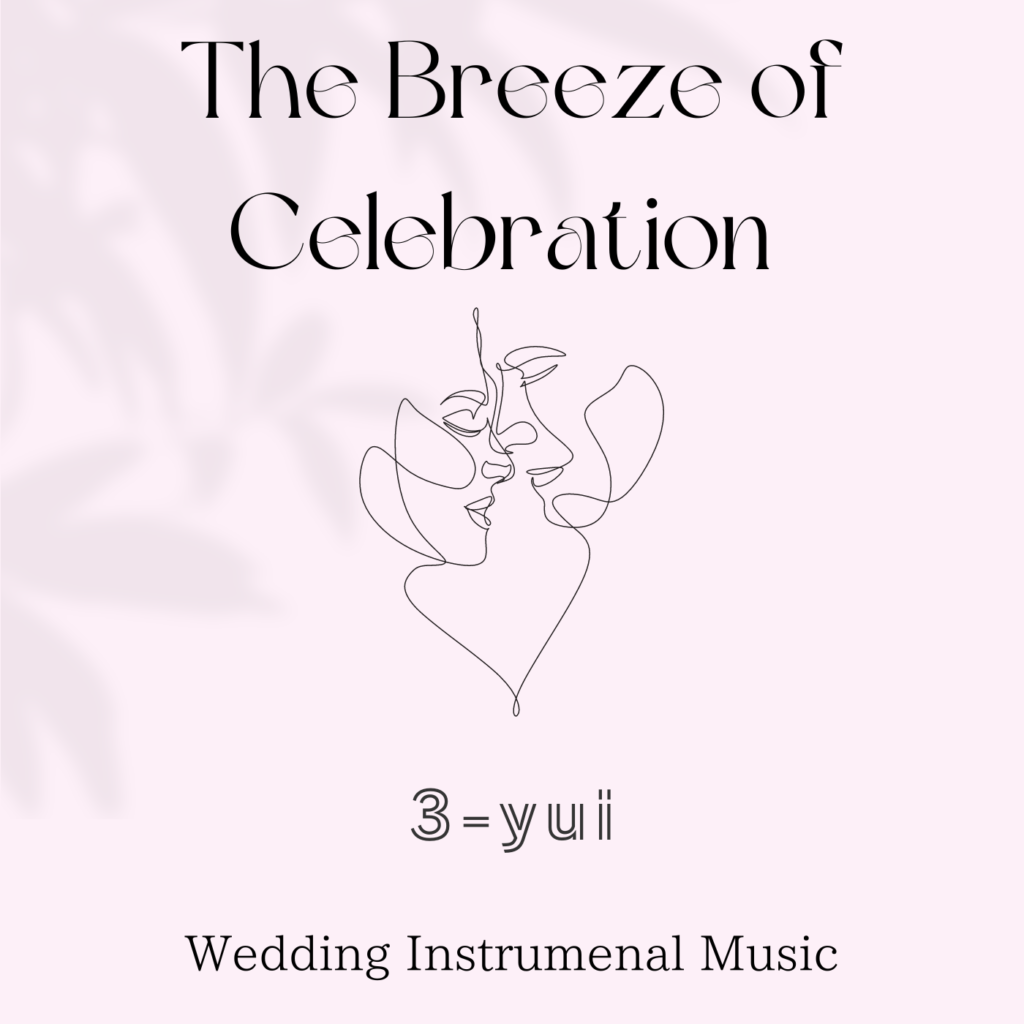
https://3-yui-sound.wedding-bgm.jp
結婚式のためのオリジナル著作権フリー楽曲の販売とストリーミング配信中!
ウエディングが
- 「人」を結ぶ(人との絆、出会い)
- 「場」を結ぶ(一堂に集まる)
- 「時」を結ぶ(過去、現在、そして未来)
この3つの結びの帯が”音楽”であるというコンセプトのもと楽曲を制作しています♪
販売サイトでは、音源の他、ジャケット写真、音源利用許諾書をパッケージして販売しています。
Apple MusicやSpotifyなどのストリーミング配信もしているので、是非3-yuiでチェックしてみてください!
◆プロフィールムービー「ナナイロウエディング」
リーズナブルな価格でプロフィールムービーを制作するなら「ナナイロウエディング」がおすすめ!
私が働いている結婚式場でも、式場提携の映像制作会社、新郎新婦や友人による手作りでの制作を除く、外注の映像制作会社による制作の中でも、もっとも多くお持込みされる制作会社の1つがこのナナイロウエディングです。
披露宴にプロフィールムービーを取り入れる割合は9割以上!新郎新婦のおふたりでご自作でされる場合も多いですが、結婚式の準備は何かとやることが多く、想定していた以上に映像制作に多くの時間を割けないのもまた事実。また映像制作に慣れていないと、文字切れや音飛び、オーサリング作業(DVDに焼く作業)でエラーが起きたり、修正しなければいけないことも結構多いです。
そういう意味でもリーズナブルな価格でプロクオリティーの映像が作れるので、是非検討してみてください。
投稿者プロフィール

-
澤近 竜佑 / Ryosuke Sawachika
ウエディングサウンドコーディネーター / 音響オペレーター / ブライダル専門学校非常勤講師 / 作曲家
明治学院大学文学部芸術学科卒業(音楽学専攻)
音楽活動や作曲活動を経て、2015年より東京、横浜エリアを中心にホテル・ウエディングの音響担当として勤務。
2020年9月、一般社団法人ウエディングミュージックコンサルタンツ協会(wmca)主催
「ウエディングミュージックアドバイザー」の認定資格を取得。
ウエディングサウンドコーディネーターとして、これまで600組以上の披露宴のBGMをコーディネート。
2023年より、3-yui名義で結婚式のためのオリジナル著作権フリー楽曲販売サイト「3-yui sound」を運営。
最新の投稿
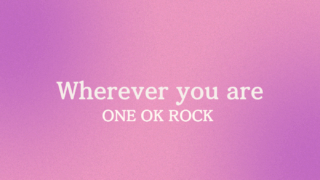 ONE OK ROCK2025年5月8日Wherever you are – ONE OK ROCK
ONE OK ROCK2025年5月8日Wherever you are – ONE OK ROCK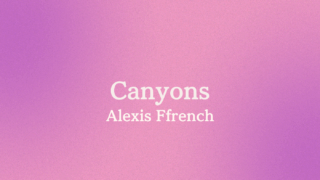 Alexis Ffrench2025年4月24日Canyons – Alexis Ffrench
Alexis Ffrench2025年4月24日Canyons – Alexis Ffrench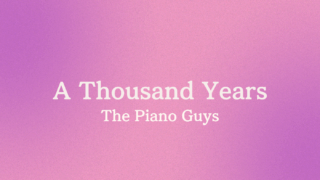 The Piano Guys2025年4月22日A Thousand Years – The Piano Guys
The Piano Guys2025年4月22日A Thousand Years – The Piano Guys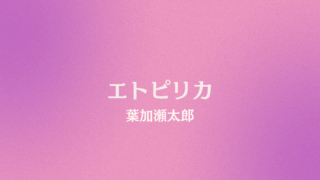 葉加瀬太郎2025年4月22日エトピリカ – NH&K TRIO
葉加瀬太郎2025年4月22日エトピリカ – NH&K TRIO